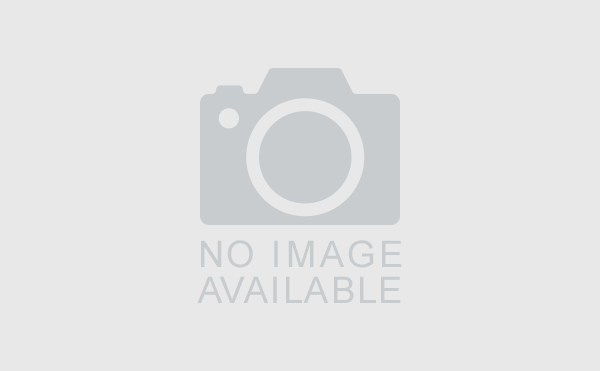第32回大会ワークショップのご案内
□開催日時:2025年6月1日(日)午後
(プログラム編成中であり開始時刻が決まり次第情報をアップします。12:30〜13:00から開始予定)
□会場:広島大学東千田キャンパス
□申し込み方法:大会プログラムが確定次第お知らせします。
島から構想するトランザクションの知恵──海-島、周囲-人間、複数-単体といった視点から
・企画者:松本光太郎(茨城大学)・南博文(筑紫女学園大学)
・話題提供:澤田英三(安田女子大学)
・小島康生(中京大学)
・大村高広(茨城大学)
・指定討論:呉宣児(共愛学園前橋国際大学)
・岩佐明彦(法政大学)
広島で初めてMERA大会が開催される。広島には地理的・歴史的・建築的に様々な特徴がある。それらの特徴のなかで、本ワークショップでは瀬戸内の海に「広(がる)島」を取り上げることにした。MERAで島という環境を取り上げたことはおそらくこれまでなかった。
日本は大陸とつながっていない島国で、およそ14,000の島があり、まさに群島の様相をもつ。島は海に囲まれている。島と海の関係はIsland-in-Seaと表記できるように不可分であり、島に注目するとき、島は図になり、海は地になる。逆に海を図として見るとき、そこは運航のフィールドになる。島に押し寄せる波や島の生態系は、海とのトランザクション※として成り立っている。
そして、島の住人は海で隔てられた陸地や周辺の海で生活を営む。人間を含めた動物が周囲(surrounding)において成り立っていることは生態心理学のギブソンが明示していたことであった。Person-in-Islandである島の住人において実現する行為やものの考え方には、周囲-人間のトランザクションとしての知恵が見出されるのではないか。
それらの知恵は住人単体に見出せるものもあれば、複数、つまり住人のコミュニティやパブリックにおいて見出されるものもあるはずである。また、島での生活は島単体で成立することは難しく、物流や観光といった他の島との交通が欠かせない点で島も複数で成り立っている。
本ワークショップでは、島や島で生きる人間に注目して、海-島、周囲-人間、複数-単体といった視点から島におけるトランザクションの知恵を構想してみたい。
話題提供は実際の島の暮らしをフィールドワークする2つの心理学研究に、島を都市の空間モデルとして打ち出した建築理論をぶつける。異なる領域・アプローチにみえるが、お互いに影響し新たなトランザクションが期待できる楽しみなラインナップになった。
話題提供者の1人目は澤田英三さんである。本ワークショップで島を取り上げるきっかけは、澤田さんが長らく広島・豊島や三重・答志島で子ども・青年や漁師のフィールドワークに取り組んできたことがある。
2人目は小島康生さんにお願いした。「沖縄県多良間島における村民運動会での乳幼児と地域の人々との関わり」(外山紀子さんとの共著)をMERAジャーナル最新号にタイミングよく発表された。かねてより多良間島の子どもたちを研究するグループには注目していた。
3人目は非会員である建築設計・建築批評の大村高広さんをお招きする。大村さんは磯崎新やイタリア・ヴェネチアの建築史家に依拠して、近代都市とは異なる「群島」という複数の島が集まる空間モデルを構想している。5月から開幕するヴェネチア建築ビエンナーレ(キュレーター:青木淳)の出品者でもある。
指定討論は原風景研究を韓国・済州島で行った呉宣児さんと、建築デザインを現地や利用者のフィールドワークから導き出す岩佐明彦さんにお願いした。
※トランザクションは環境心理学のなかで長らく議論されてきた研究の単位であるが、ここでは簡潔に「その場所で実現する行為やものの考え方」という意味で使用している。